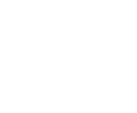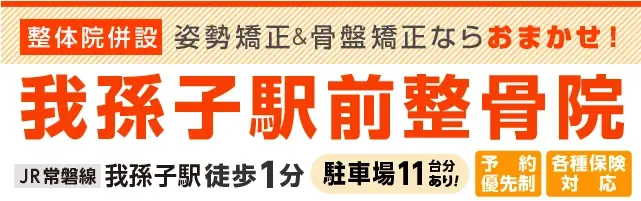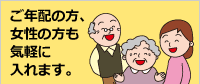オスグッド


こんなお悩みはありませんか?

膝のお皿の下に熱感と腫れがあり、圧痛が感じられる
ジャンプや走る動作をした際、膝下に強い痛みが走り、屈伸動作が困難になる
子供の膝下に骨性の膨らみができ、運動後に足を引きずることがある
運動時に膝下に痛みがあり、運動をしていないときは痛みがない
オスグッドの影響で、下半身の動きがうまく使えず、上半身との連動が悪くなる
オスグッドにより、他の部位の怪我が増えることがある
オスグッドについて知っておくべきこと

オスグッドはただの成長痛と勘違いされることが多いですが、無理して運動を続けると痛みや腫れが取れにくくなり、運動を長期間休まなくてはいけなくなることがあります。最悪の場合、外科的な手術が必要になるケースも考えられます。
オスグッドは、成長期の未成熟な骨に起こりやすい症状です。これは骨が成長する過程で、骨端核と呼ばれる強度の弱い部分が存在しているためです。未成熟な骨の状態で過度な運動を繰り返すと、大腿四頭筋が停止する脛骨粗面に負荷がかかり、軟骨が剥離してしまいます。
オスグッドは、小学校高学年から中学生にかけて起こりやすく、膝を過度に使う競技で症状が現れることが多いです。また、痛みが出る場所を確認することで、成長痛との鑑別がしやすくなります。
症状の現れ方は?

オスグッドの症状は、急に膝の下に痛みが現れることが特徴です。運動時や運動後に痛みが出始め、次第に脛骨粗面の突出が見られるようになります。発生初期には、屈伸時や走った時に脛骨粗面に痛み、熱感、腫れなどの違和感が現れますが、運動が全くできないほどではないことが多いです。
しかし、無理をして症状を放置すると、痛みが重症化し、運動時や安静時にも痛みが現れるようになり、痛みがなかなか緩和しにくくなります。また、学生時代の成長期に無理をした結果、骨端線が閉鎖した後でも、大人になってから運動時や運動後、さらには安静時にも支障をきたす後遺症に悩まされることがあります。最終的には、満足に運動ができない状態に繋がる可能性があります。
その他の原因は?

オスグッドは成長期に発症することが多いため、ただの成長痛と勘違いされることがよくあります。その結果、本人や指導者の認識が甘く、無理をして運動を続けさせてしまうケースが多く見受けられます。これが、症状が進行し、最終的に慢性化してしまう原因の一つとなります。
オスグッドは早期に発見し、初期症状の段階で大腿四頭筋のストレッチやアイシングを行い、脛骨粗面にかかる負荷を最小限に抑えることが重要です。炎症が一時的に落ち着いたからといって、無理に運動強度を下げずに継続して行うこともありますので注意が必要です。
また、普段の部活内でのクールダウンの時間が十分に取れていない傾向もあり、これが症状の悪化を招く原因となることがあります。
オスグッドを放置するとどうなる?

オスグッドを放置していると、膝の下にある脛骨粗面と呼ばれる部分が徐々に突出し、腫れ、熱感、動作時の痛みなどが現れるケースがほとんどです。痛みを我慢しながら運動を無理に続けることで、脛骨粗面に付着している大腿四頭筋が成長軟骨を引っ張り、脛骨粗面にかかる負担が増大します。最悪の場合、剥離骨折を引き起こすこともあります。
時間が経過して痛みが軽減したとしても、運動をするたびに痛みが再発し、慢性化してしまうことがあります。その結果、満足に運動ができなくなったり、飛び出した脛骨粗面を削る手術が必要になることもあります。
当院の施術方法について

当院のオスグッドの施術方法としては初期の段階で熱感や腫れがある場合、第一に脛骨粗面のアイシングをし患部の安静を保ちます。症状が初期であれば練習量を減らしたり脛骨粗面に負担がかかる動作を制限させたりテーピングを施しながら症状の緩和を目指します。また、オスグッドの原因でもある大腿四頭筋の他動的ストレッチや手技療法、電気療法によって筋肉の柔軟性と筋緊張の緩和を目指していきます。最後にオスグッドは単なる成長痛と認識されていることが多く理解がされていない症状でもあるため親御さんにもしっかりと症状の説明をし子供に無理をさせない指導をしていきます。
改善していく上でのポイント

成長期による過度の運動(オーバーユース)が原因で、大腿四頭筋が脛骨粗面の成長軟骨を引っ張ることがオスグッドの原因となります。そのため、大腿部前面のストレッチを入念に行い、柔軟性を保つことが非常に重要です。セルフケアとして、運動前後で大腿部のストレッチを行い、熱感や腫れが見られる場合にはアイシングを必ず行いましょう。また、テーピングやオスグッド用のバンドを膝蓋靭帯を抑えるように装着し、脛骨粗面にかかる負担を軽減することが大切です。
さらに、オスグッドは早期に治療を行うことで慢性化を防ぎやすくなります。したがって、適切なトレーニングメニューを立てることも重要です。
監修

我孫子駅前整骨院 院長
資格:柔道整復師
出身地:新潟県三条市
趣味・特技:サッカー観戦、音楽鑑賞、買物